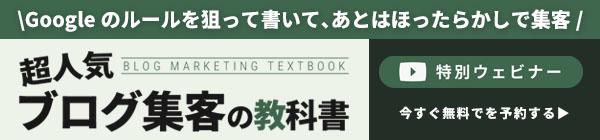ジョイントベンチャーのメリットとは?パートナーの選び方と事例を紹介!
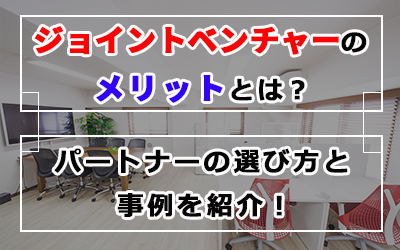
皆さんAmazonって使ったことありますか?
本当に何でもある!と思うほど品数が多く大体の買い物はAmazonだけで終わらせることができちゃいますよね。
好きなアーティストのCD予約をAmazonでする人も多いですよね。
特典がついてたりするのでなんだかお得な感じもしちゃったりするんです。
本とかも予約ができて無いものはないのか?!と思ってしまいます。
クリエイターの作品がないくらいでしょうか?
でも中にはAmazonで販売している方もいるのでやっぱりほとんどの物が売っていますね。
そんなAmazonですが、「ジョイントベンチャー」という手法を用いています。しかもそれで大成功しているのです。
今回はジョイントベンチャーのメリットやパートナーの選び方、事例を紹介していきます。
ジョイントベンチャーについても説明しますのでご一読ください!
Contents
ジョイントベンチャーとは

合弁企業とも呼ばれ、複数の企業が共同で出資を行い、新規事業を立ち上げることを意味しています。
2つの形態があり
①企業それぞれが出資して新しい企業を立ち上げ、協働で経営する。
②既存企業の株式の一部を買収して、既存の株主・経営者と共同で経営する。
となっています。
基本的には①の形態が多く選ばれます。
各企業が出資を行ってコラボという形で行われることもあります。
M&Aとの違い
M&Aとは、Mergers(合併)and Acquisitions(買収)の略です。
企業の合併や買収のみならず提携までを含める場合もあります。
0から事業を作るのにかかる時間を買って、自社ビジネスとの相乗効果を発揮させ、競合に対する優位性を早期に確立することが目的となります。
ただし吸収しているので関係の解消というのはかなり困難です。
M&Aとの違いは、影響力でしょう。
M&Aの場合、取り込んだ企業が全ての資本を有しているために多大な影響力を持ちます。
ですが、ジョイントベンチャーの場合は共同出資なので思い通りに動かせるような影響力は持てません。そのためM&Aと比べると双方の意向を汲みこむ必要があるので、自社にとっての自由度というものは変わってきます。
アライアンスとの違い
アライアンスとは、複数の企業がお互いの経済的なメリットを享受するために緩やかな協力体制を構築することを言います。
M&Aと違って時間や資金をそこまで要さずにすみ、思惑が外れても関係を容易に解消できてしまいます。
アライアンスとの違いは、解消の難易度と強制力です。
アライアンスの場合は協力体制で特に出資の必要がないため、思うような効果が出なければすぐに関係を解消できてしまいます。そのため強制力は弱くなり各企業の働き次第で左右されます。
ジョイントベンチャーは出資がある分、関係の解消はそこまで容易にはいきません。当然、強制力も働きます。簡単そうに見えてしっかりと関係をつないでいるので、
ジョイントベンチャーはM&Aとアライアンスの間に位置するものと言えます。
似ている面があり混同しがちですが、違うものです。混合しないようにお気を付けください。
ジョイントベンチャーのメリット

コスト
まず間違いなく言われるメリットがコスト面です。
自分一人で新しく事業を立てたり買収する場合、自分一人が出資しなければなりません。
ですが、合弁企業としてならば複数の企業で出資する形になりますので必然的にコストが抑えられます。
また、コストを抑えられた分負うリスクも軽減できるということになります。
提携先の強みを活用できる
自社が持っていなくてもパートナーとなる相手企業が持つリソースを活用することができます。ブランドやインフラ、ノウハウを活かして事業を進められます。
これを目的にジョイントベンチャーをするといっても過言ではないかもしれません。
1からリソースを作ることなく相手の者を活用できれば非常に楽になるといえます。
もちろん相手にとっても自社のリソースを利用できるという事になります。
信用を借りられる
パートナーとなる相手が持つ信用を借りることも可能なのです。
違うファン層をであればお互いに利用できますし、中小企業が大企業と組めばそのネームバリューを借りれるというわけです。
集客は難しいものですが、このように借りれてしまえば少しは楽になりますね。
海外進出が容易に
外資企業のみで企業設立が禁止されている国にも、合弁企業を通して進出できてしまいます。
ここで魅力的なのが、現地のパートナーである相手企業が持つその国独自の法律・ルールへの対応や、トラブルの対処などのノウハウを得ることができます。
なかなか文化の違いは難しくありますが、その国で商売をする以上知っておかなければなりません。最初からわかっていればかなり楽ができるでしょう。
デメリットは?
メリットはわかったけどデメリットはないの?と思いますよね。
当然ですがあります。
ノウハウや技術の流出
これまで開発してきた技術やノウハウが相手の企業へ流出してしまう可能性があります。
どこからどこまでを合弁企業に提供するか、そしてパートナーを誰にするかは慎重に調べて考える必要があります。
方針をめぐるトラブルへの対処
いくらどちらかが多く出していたとしても、出資していることに変わりはないので双方の意向を汲む必要があります。
親会社と子会社のような支配関係がないので、上手くまとまらなければ対立状態になることもあるのです。
得られるものがある反面、当然リスクがあります。
1番リスクを避けられ、効果を発揮できそうなパートナーを慎重に探すことが必須となります。
パートナーは競合から見つけよう

ではパートナーはどう見つけたらいいのでしょうか?
ズバリ競合他社です。
競合他社にも種類があり
・直接競合・・・同事業者でほとんど同じものを取り扱っている競合
・間接競合・・・同業者で類似ではあるが取り扱うものが違う競合
の2つとなります。
そしてジョイントベンチャーのパートナーとして選ぶべきは間接競合です。
同じ業界で取り扱うものが違うとなると、今までできていなかったところに手を出せるようになるというわけです。提供するノウハウも別のものになるので新しい事業を開始できます。
ここで直接競合を選んでしまうと今までやっていたことと似たことしかできず、意味がりません。だったら吸収合併でもして規模を広げる方に方針を決める方が堅実でしょう。
そして大切なことですが、目的が同じ人と組むようにしてください。目的が違う人と組んでもうまく行くはずがありませんし、事業を進めていくとすぐに壁に当たるでしょう。絶対に目的が同じ人をパートナーとしてください。
自分はどのタイプ?

ジョイントベンチャーを行う上で、自分がどのタイプなのか?を知っておくとパートナー選びや方針を決めるときに役立ちます。
①自分の商品を売ってもらう・・・自社製品はあるが販売できる場所がない
②代わりに商品を売ってあげる・・・販売場所はあるが提供する商品がない
③何かする代わりに、なにかする・・・お互いに分業などをして支えあえる
④ジョイントベンチャーを求める人を繋げてあげる・・・例えば①の人と②の人を繋げる
4つのタイプ分けができます。
自分がどれか?を考えてみてください。その場合どのタイプがパートナーとして欲しいか?と考えます。そこから競合を調べ、目的や方針が合うところとパートナーになるという流れができます。
非常にざっくりとした分け方ではありますが、指標の一つとして見れますので覚えておいてください。
ジョイントベンチャーの事例
■Amazon
Amazonはプラットフォーム・顧客リスト・知名度を提供し、企業から商品・コンテンツを提供してもらう形で運営していて、売上の何%かを受け取るという形になります。
先ほどのタイプ別に言えばAmazonは②で、パートナーの企業が①となります。
あれほど有名で利用者も多い会社ですので、企業からすればより多くの人に見てもらえる機会が増えると考えます。そう考えた企業がパートナーになり、を繰り返すと商品展開がさらに幅広くなりより利用者が増えるというわけです。
■自動販売機
自動販売機は販売機器の提供を、メーカーは商品の提供を、土地の保有者は販売場所の提供をして、売り上げを分配します。
タイプ別に言えば自動販売機は②、土地の保有者も②でメーカーが①です。
自動販売機と土地の保有者の関係は③に近いかもしれません。
それぞれが持つものを気軽に魅力的に販売する良い例ですね。それぞれ最初に提供したリソースがあるだけで、後は売り上げの分配をして回収するだけになります。
大きな出資が無くてもできるという事になります。
■ビックロ
ビックカメラとユニクロがコラボして作ったブランドです。
どちらも大手企業であることからもちろんそのブランド力やファンを提供していることになります。
ビックカメラのポイントをユニクロのクーポンに変換できたりなど、お互いの既存客に訴えかけるようなサプライズを用意しています。
タイプ別にいうと③の関係になるでしょう。
お互いにファンや強みを提供して事業展開していく形をとっています。
中小企業が行うイメージの強いジョイントベンチャーですが、大企業でも行います。
今回の場合で言えば話題性があること、そして一等地のビルを1棟借りても経費を折半できるというメリットがありますね。多面的に見ても効果が見込める事例です。
まとめ
今回はジョイントベンチャーのメリット・デメリットとパートナー選びや自分のタイプ、事例について紹介していきました!
いかがでしたか?
ノウハウや技術の流出とパートナー選びにさえ気を付けていればメリットの大きい手法だといえます。
大企業でも新しい取り組みとして行っている例がありますので、やり方さえ間違えなければ効果を発揮できるでしょう。
メリットとデメリットを考えつつ、自分の目的にあったパートナーを競合の中から調査してジョイントベンチャーをしましょう!過去の事例から方針を決めるのも良いですね。
今チャレンジしたいことがある方はぜひ検討してみてください。
それでは次回のブログをお楽しみに!